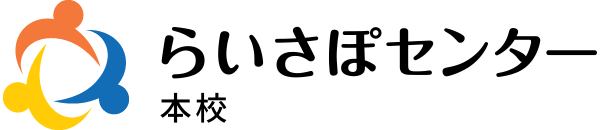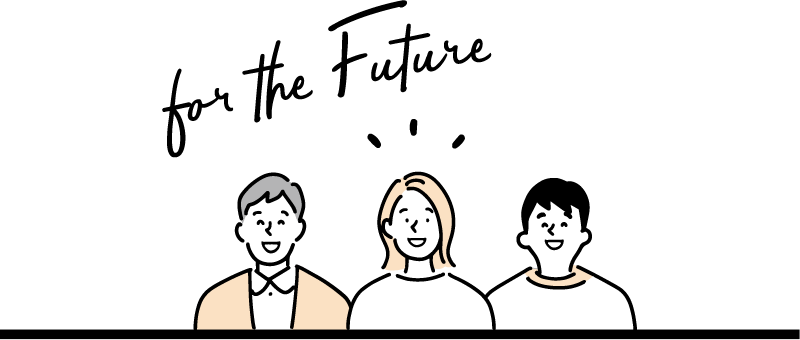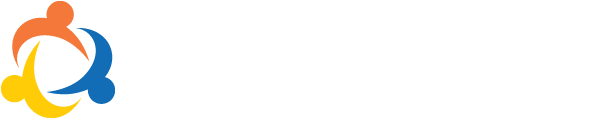「過干渉な親にはどんな特徴があるの?」
「過干渉は子どもにどんな悪影響があるか知りたい!」
親なら誰でも子どものことが心配で、行動や選択についつい口を出してしまいがちです。
しかし、行き過ぎた干渉は子どもがやる気をなくす原因になってしまいます。
そこで本記事では、過干渉が子どもへ与える悪影響を5つ紹介。過干渉な親の特徴についても解説するので、自分が当てはまっていないかチェックしてみましょう。
この記事でわかること
こんな人におすすめの記事です
- 自分が過干渉かもしれないと感じている方
- 過干渉に悩む方の家族・友人
- 過干渉を治したいと思っている方
親の過干渉とは?
まずは過干渉とはどういう状態なのか知りましょう。
過干渉とは文字通り干渉しすぎることです。子育てにおいては、子どもの行動を制限しすぎたり、親の理想を子供に押し付けすぎたりすることを指します。
過干渉な親は、子どもの意思を無視して思い通りにコントロールしようとするため、子どもがストレスを抱え込みやすいです。
そして過干渉な状態を放置すると、子どもが自分で考える力が育たないため、無気力になったり、自信が持てなくなったりします。
また、親は子どものためを思って行動しているため、自分の過干渉な子育てになかなか気づきません。
定期的に自分が過干渉になっていないか振り返る時間を作りましょう。
過保護との違い
過干渉と似た言葉に「過保護」があります。
過保護は子どもの「やりたい」「やりたくない」という言葉を、甘やかしてそのまま受け入れてしまう状態です。
過保護は自分のやりたいことをやらせてもらえるため親の愛情を感じやすいですが、過干渉は自由を奪われるため親に対して怒りを感じる子どもが多い傾向にあります。
また、子どもが望んでいることを親が受け入れて叶えようとする点が過干渉とは異なります。
過干渉と過保護のいずれも、子どもの自立が遅れる恐れがあるため、行き過ぎた行動には注意しましょう。
過干渉をする親の心理とは?
過干渉をする親の心理は、愛情や守ってあげたい気持ちが強すぎて、子どもに対する心配や不安が過剰になっていることが多いです。
「子どもに失敗させたくない」「自分が苦労した経験をさせたくない」といった思いが、過剰な干渉につながることがあります。
また、親自身の自己肯定感が低い場合、子どもの成功を通じて自分の価値を確認しようとし、子どもの行動を細かく管理したり、期待を押し付けたりするのです。
さらに、他人の評価を気にしすぎる親ほど、子どもが「完璧でなければならない」と考えます。
過干渉を防ぐには、親自身が自分の感情や考えを振り返り、子どもを信頼して見守る姿勢を持つことが大切です。
過干渉な親の特徴
過干渉をする親の心理がわかったところで、具体的な過干渉な親の特徴を5つ紹介します。
過干渉な親の特徴5選
自分が上記のような特徴に当てはまっていないか振り返ってみましょう。
①子どもの行動を細かくチェックする
過干渉な親は、子どもがミスを犯したり、間違った選択をしたりすることを避けるため、必要以上に行動を把握しようとします。
子どもが何をしているのか、誰と一緒にいるのか、どんな話をしているのかなど、気になる気持ちはわかりますが過度な監視は子どもの自立心を妨げる可能性が高いです。
子どもは「信じてもらえない」と感じると、親との間に距離を置こうとしたり、逆に依存したりします。
適度な距離感を保ち、子供の行動を見守ることが大切です。
②子どもの失敗を許さない
子どもが間違いや失敗するたびに厳しく指摘したり、未然に失敗を防ごうとすると、子どもは「失敗は悪いことだ」「自分には何も任せてもらえない」と感じるようになります。
このような環境では、子どもは挑戦を恐れるようになり、新しいことに取り組む意欲や自信を失ってしまう可能性が高いです。
失敗から学ぶことは多いため、親がその経験を奪うことは、子どもの自立心や問題解決能力を育ちにくくさせます。
親は失敗を受け入れサポートに徹し、子どもが成長できる環境を作ってあげましょう。
③子どもの選択を制限する
親が「これが正しい道だ」と決めつけ選択を制限すると、子どもが自分で考え決断する力が養われません。
子どもは「自分の意見は尊重されない」「親が満足するように動かないといけない」と感じるようになり、自信や主体性を失う可能性が高いです。
さらに、選択肢が制限されることで、子どもは新しい挑戦や経験ができなくなり、成長の幅が狭まることがあります。
親は子どもの行動や選択を尊重し、意見に耳を傾けてあげましょう。
④子どもの交友関係に口を出す
過干渉な親は、子どもの交友関係に対して過剰に口を出すことがあります。
「あの子とは付き合わないで」「この友達ともっと仲良くしなさい」といった形で、交友関係をコントロールしがちです。
子どもの交友関係に口を出しすぎてしまうと、友達の自然な作り方や関わり方がわからなくなってしまいます。
また、「自分の判断は信用されていない」と感じ、自己肯定感が下がる可能性が高いです。
できるだけ子どもには自分で友達を作る経験をさせてあげましょう。
⑤褒めるよりも叱る方が多い
子どもの行動や成果を褒めるよりも、欠点を探して叱ることを優先してしまうと、子どもは「何をしても満足してもらえない」と感じるようになります。
そして、叱られることを恐れるあまり、新しいことに挑戦する意欲を失ってしまいます。
また、褒められる機会が少ないと、自分の長所や成功に気づきにくいです。
親が意識的に褒めることで、子どもの成長や、やる気を後押しできます。
子供に完璧を求めすぎると萎縮し、チャレンジする気持ちを奪ってしまうため注意しましょう。
親の過干渉が与える子どもへの悪い影響5選
どのような行動や言動が過干渉になってしまうのかわかったところで、ここからは過干渉が与える子どもへの悪い影響を5つ紹介します。
親の過干渉が与える子どもへの悪い影響5選
それぞれ確認していきましょう。
①自立できなくなる
親が子どもの行動に干渉し過ぎると、自分で判断する機会がなくなり「どうすればいいのかわからない」「親に相談しないと決められない」状態になりやすいです。
社会に出たとき自分で考え行動する力が求められるため、親に判断を委ねたまま成長してしまうと苦労します。
幼い間は親がある程度決めてあげるのは問題ありませんが、大きくなるにつれて自分で考える時間を作ってあげましょう。
②自己肯定感が下がる
子どもが自分の選択や行動に対して否定的な評価を受け続けると、「自分では何もできない」と感じるようになりがちです。
例えば、親が過度に細かく指示を出したり、子どもの失敗に厳しく反応したりすると、子どもは自分の努力や成果を認めてもらえないと感じるようになります。
その結果、「どうせ自分には無理だ」「誰かに頼らないとダメだ」と自己肯定感が下がります。
できるだけ子どもの意思を尊重して、サポートしてあげましょう。
③いじめの加害者になる
親からの過干渉は子どもをいじめの加害者にしてしまう可能性があります。
子どもは親からの過干渉を受けると、自分の感情や欲求を抑え込もうとしストレスを溜め込みます。
その結果、抑えきれないストレスや不安がいじめという攻撃的な行動として現れるのです。
また、親が子どもをコントロールする姿を見ているため、友達に対しても同じような行動をしてしまう場合もあるため注意しましょう。
④やる気がなくなる
親の過干渉は、子どもの「やる気」を奪う原因となります。
親が子どもの行動を全て先回りして決定したり、細かく指示を与えたりすると、子どもは自分の意志で行動しなくなります。
「どうせ自分で考えても無駄」「親が決めるから意味がない」と感じてしまうからです。
また、親の期待に応えることばかりを求められると失敗を恐れ、新しいことに挑戦したいという気持ちが薄れます。
毎回行動を否定されてしまうと、大人でも無気力になります。親の中で答えが決まっているなら、自分で考えるのは無駄だと感じてしまうのは当然です。
親は子どものサポートに徹し、できるだけ自分で考え行動し、成功する体験を積ませてあげましょう。
⑤親の顔色ばかり気にする
親の過干渉は、子どもが親の顔色ばかり気にする性格にしてしまう可能性が高いです。
管理された環境で育った子どもは、親の期待や評価を常に意識するようになり、「これをしたら怒られるかもしれない」「どうすれば喜んでもらえるだろう」といった考えが頭をよぎり、自分の意志や感情を抑え込んでしまいます。
その結果、子どもは自分の判断ではなく、親の反応を基準に行動するようになり、自律性や主体性を失いやすくなってしまうのです。
また、社会に出た時も上司や部下の顔色ばかり伺ってしまい、ストレスを溜め込みやすくなってしまいます。
子どもが親の顔色を伺って行動しているなと感じたら、子どもが本当に望んでいることを汲み取り、できるだけさせてあげましょう。
過干渉な親にならないためのポイント3選
親の過干渉は子どもに様々な悪い影響を与えます。ここでは過干渉な親にならないためのポイントを3つ紹介します。
過干渉な親にならないためのポイント3選
自分が過干渉な親にならないためにも、できることから取り組んでいきましょう。
子どもの行動を見守る
過干渉な親にならないためには、子どもの行動を見守る姿勢が大切です。
子どもの選択や行動を尊重しつつ、必要なときだけサポートしましょう。
例えば、子どもが挑戦しようとしている場面で、失敗や間違いを急いで指摘するのではなく、まずはその行動や失敗から学ぶ過程を見守りましょう。
子どもは自分の力で考え、問題を解決する能力を磨いていきます。
また、親が余計な介入を控えることで、子どもは「信頼されている」と感じ、自己肯定感や自立心が育ちます。
見守ることは決して無関心ではありません。子供とは適度な距離感を保ち、行動を見守りましょう。
子どもの意思を尊重する
親が過干渉にならないためには、子どもの意思を尊重する姿勢が大切です。
子どもが自分で考え決断する力を育てるためには、親が子どもの選択をできるだけ受け入れましょう。
進路や就職先の選び方など大切な決断に対して親が指示を出すのではなく、子ども自身の考えや希望を聞き、それに基づいてアドバイスする姿勢が大切です。
たとえ失敗する可能性があっても、その経験から学ぶことで子どもは成長します。
また、自分の意思が尊重されることで、子どもは「信じてもらえている」と感じ、自己肯定感が高まるでしょう。
親が子どもの選択に過剰に介入せず、見守る心の余裕を持つことが、良い親子関係を作る秘訣です。
自分の言動を定期的に振り返る
自分が過干渉にならないためには、自分の言動を定期的に振り返ることが大切です。
日々の生活で子どもに対してどのような言葉を使い、どれだけ介入しているかを冷静に見直すことで、知らず識らずのうちに過干渉になっていないかを確認できます。
たとえば、「この行動は本当に子どものためになっているか」「自分の不安や理想を押し付けていないか」自分の行動や言動をリストアップし振り返ることで、過干渉になっていなか確認できるでしょう。
親自身が一度冷静になって自分の言動を振り返ることで、子どもの自主性を尊重する余裕が生まれ、過干渉を防げます。
親が過干渉になってしまったときの対処法
ここからは自分が過干渉になってしまった場合の対処方法を紹介します。
親が過干渉になってしまったときの対処法
自分が過干渉になってしまっていると感じる場合は、以下で紹介する対処方法を試してみましょう。
親子の間にルールを作る
過干渉な親への対処法のひとつに「親子の間にルールを作る」があります。
具体的には、「子どものプライバシーに踏み込みすぎない」「話し合いの場を設ける」などのルールを話し合いの中で決めることで、親の過剰な干渉を防げます。
具体的なルール案
- 相手の意見を最後まで聞く
- 日記やスマホの中身を許可なく見ない
- 毎週〇曜日の夕食時など、親子でお互いの考えを話し合う時間を作る
- 感謝の気持ちは素直に伝える
- 目標を共有する
- 感情的になったときは距離を取る
- 無理な約束をしない など
ルールを決める際のポイントは、親が子どもの意思を尊重しつつ、適切な距離感を保てるかがポイントです。
また、ルールを明確にすることで、親もどの程度干渉すべきかわかりやすくなります。
子どもの意見をじっくり聞く時間を作る
定期的に子どもの意見をじっくり聞く時間を作りましょう。
「これは自分で決めたい」「こうしたいと思っている」などの意見をしっかり受け止めることで、子どもなりに考えていることがわかります。
子どもの意見を聞くときは、口出ししたくなると思いますが、一度最後までしっかり聞いてあげるのがポイントです。
ただし、感情的に意見を述べさせるのではなく「自分にとってこれが良い理由」を具体的に説明させましょう。子どもの考える力や説明力が身につきます。
そして、説明の筋が通っているなら、ある程度子どもの意思を尊重してあげることが大切です。
意識して時間を作らなければ、子どもの意見をじっくり聞くタイミングはなかなかありません。
自分から時間の都合をつけて定期的に子供が何を考えているのか話あってみましょう。
相談相手を作る
どうしても子どもの行動に口を出さずにはいられない過干渉な方は、自分一人で悩まずに誰かに相談してみましょう。
第三者に話を聞いてもらうことで気持ちが整理され、自分一人では思いつかなかった対処法が浮かぶかもしれません。
相談相手には友人や教師、信頼できる親戚など、親子関係の状況を冷静に見てアドバイスをくれる人を選ぶことが大切です。
また、相談相手がいることで、自分の感情や意見を言語化でき、子どもと向き合う際により良い対話ができるようになります。
知り合いに悩みを相談するのが恥ずかしいと感じる方は、カウンセラーなど専門家の助けを借りるのも良いでしょう。
お住まいの地域ごとに子育てに関して相談できる窓口は異なります。
こども家庭庁の相談窓口一覧のページを参考に相談先を探してみましょう。
また、過干渉によって子どもが引きこもり気味になってしまっている場合は、民間の支援団体に相談するのもおすすめです。
「らいさぽセンター」は引きこもり、ニート、不登校児のための就労・学習・自立支援を行う全寮制の施設です。
全寮制の施設のため、子どもが自分で考えて行動する力が養われます。
子どもと一度距離を置いて自分を見つめ直す時間を作るのも良いでしょう。無料で相談を受け付けているので、気になる方は気軽に問い合わせてみましょう。
まとめ:過干渉に悩んでいるなら相談しよう
今回の記事では過干渉な親の特徴や子どもに与える悪影響について解説しました。
親の過干渉が与える子どもへの悪い影響5選
親の過干渉は子どもの自立心や挑戦心を阻害してしまい、やる気を失わせる原因となる可能性が高いです。
このような状態にならないためにも、親子間でしっかり話し合い、子どもの意見に耳を傾ける時間を作ることが大切です。
また、どうしても自分の過干渉な性格が治らなくて困っている方は、カウンセラーなど専門家の助けを借りるのも良いでしょう。
こども家庭庁の相談窓口一覧のページを参考に相談先を探してみましょう。